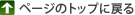特別寄稿 (サラーム・キルギスツアー2011夏レポート)
特別寄稿
「サラーム・キルギスツアー2011夏 −天山の真珠に触れて−」
文・写真: ジャーナリスト 佐藤慧さん (スタディオアフタモード所属)

1.天山山脈の麓へ
キルギス共和国。多くの人はその名を聞いてもどこにあるのかさえ正確には思い浮かべることもできないだろう。僕もそうだった。2010年の政変、暴動のニュースは耳にしていた。世界のどこかで何かが進行中だという認識はあったが、その意識がキルギスという国の内部に、そこに生きている人々に向けられることはなかった。そんなニュースの中の記号としてしか捉えられなかったキルギスに、この夏飛んだ。
「キルギスに行きませんか?」
そんなメッセージが突然送られてきた。日本とキルギスの交流のために、毎日エデュケーション社がツアーを開催するという。実はキルギスは大変な親日国で、この度の震災でもいち早く東北地方に飲料水を送っていたという。僕自身家族が被災した身として、そんな場所もわからない国の会ったこともない人々が日本のことを想っていてくれたという事実に衝撃を受けた。「震災に関する講演も行って欲しいのです」。少しでも日本で起きたことを人々に伝えられる機会、そして何より、日本のために行動を起こしてくれた人々に自ら感謝の言葉を届けられる。僕は即座にキルギス行きを快諾した。
キルギスという国に関して全く無知であった僕は、ツアー主催者のキルギス側責任者のイバラットさんが東京で講演したイベントにお邪魔することにした。彼女は流暢な日本語でキルギスの様子を説明した。その日本語力にも感銘を受けたけれど、なんといってもイバラットさんの見た目がまるで日本人のようだということに驚いた。実はキルギスにはこんな言い伝えがあるという。「昔キルギス人と日本人は兄弟だった。肉の好きなものが西へ行きキルギス人となり、魚の好きなものは東へ渡り日本人となった」。そんな話が真実に思えてしまうほど、キルギス人と日本人は瓜二つだった。ツアー開催に際し、イバラットさんは本国で準備を進めるという。写真に見た美しい光景を思い浮かべながら、キルギスでの再会を約束し、会場を後にした。
渡航の日が迫り、僕はキルギスに関する情報を集めていた。日本語の情報源は限られていたため、海外のNGOの報告書や旅行案内書にも目を通す。初めての中央アジアということもあり、中々イメージが浮かばない。実際に足を運び、この目で見て、耳で聞き、肌で感じる他はない。結局たどり着いたのはどの国にも共通するそんな答えだった。まるで遠足前の小学生のように、わくわくしながらバックパックに荷物を詰め、渡航の日を待った。
2.キルギスの家族

飛行機は遙か西へ、トルコはイスタンブールまで飛び、そこで1日を過ごした後、今度は東へ向かって飛び立った。標高800mに迫る首都ビシュケクの空気は涼しかった。猛暑の東京から比べると湿気も少なく、断然過ごしやすい気候だった。入国すると、ツアーを企画してくれた前述のイバラットさんが笑顔で出迎えてくれた。本当にキルギスに来たのだな、と安堵と共に感慨を覚える。真夜中過ぎの到着だったため、まずはホテルで体を休めることにした。
翌朝、目覚めてバルコニーから外を眺め、思わず息を呑んだ。見渡すかぎりの平野が続くその先には、雄々しい山々が連なり、壮大な景色を形作っていた。「なんて美しい国へ来たのだろう」、それがキルギスの第一印象となった。正午近くまで予定がなかったため、ホテルで朝食を取るとタクシーで町中まで出てみることにした。この美しい山々の袂で、いったいどのような人々が生活しているのか気になったのだ。

土地勘の無い僕はとりあえず街の中心地であろう駅の付近を目指すことにした。実はキルギスでは電車はほとんど用いられず、トロリーバスが主に市民の足となっていたのだが、そんなことは知らなかった。人混みの中に着くと思っていた僕の予想を裏切り、タクシーは美しい公園の傍らの駅に着いた。まばらな人影が、ゆったりと流れる時間の中を歩いていた。もう少し雑多なところに足を運びたいと思っていたが、時間も限られていたのでこの付近を歩いてみようとタクシーを降りた。朝の穏やかな陽を浴びながら、出逢う人に声をかけて歩いた。キルギスの人たちはキルギス語とロシア語を話す。当然ながら僕はそのどちらも出来なかった。しかし道行く人は、その容姿が近いこともあったためか、みな笑顔で応対してくれる。僕は日本語で話し、彼らはキルギス語で返した。何気ない朝の挨拶。言語が違っても、語り合えることはある。笑顔の彼らの瞳の奥を覗き込み、シャッターを切った。
ホテルに戻り、旅の仲間たちと合流する。今回のツアーは合計12名、年代も職業もバラバラの、個性的な面々が揃っていた。60億を越えるこの地球上で、日本に生まれ、そこから「キルギス」といいう国に惹かれてやってきた12人。縁を感じずにはいられない。そんな彼ら、彼女らと、キルギスの市場、バザールに出向くことにした。バザールには多くの人が溢れかえり、市場独特のエネルギーに満ちていた。見たこともないものが所狭しと並べられ、みな興味津々にバザールを練り歩いた。普段は海外で買い物をすることもない僕も、ひとつだけ買い物をしてしまった。それはテミルコムズという楽器。小さな金属製の楽器で、前歯に軽く挟みながら指で弾いて演奏する。その曖昧で深い振動に魅了されてしまった。バザールの人々と笑顔で挨拶を交わしながら、何種類もあるドライフルーツをつまみ食いする。「おいしい」、と笑顔を浮かべる日本人旅行者たちに、バザールのおばさんたちも嬉しそうだ。こういう何気ない交流を目の当たりにすると、普段国境だの民族や宗教だのと対立し合っている世界の構図がばかばかしく思えてしまう。目の前のあなたがいて、僕がいる。それだけなのだ。
今回のツアーの趣旨はキルギスと日本の交流の架け橋となること。夜には多くのキルギスの方が集まるパーティへと招かれた。キルギスの伝統料理に音楽、様々な催し物で会場は賑わった。そこには東北へ飲料水を支援してくれたキルギスの飲料メーカーの社長もいた。彼は日本に留学していたことがあり、今も日本に感謝し、尊敬しているという。親日国のキルギスでは、みな日本に対して尊敬の念を抱いてくれていた。それだけにこの度の震災にも心を痛め、何か出来ることはないかと思案してくれていたのだ。僕は正直、彼らが言うほどに今の日本を誇らしく思っていない。確かに日本は素晴らしい歴史と文化を築いてきたし、社会全体の生活レベルは高い。しかし既に震災を過去のこととし、目の前の享楽的な消費社会に流されていく日常があることもまた知っているからだ。また、他の国の事柄には中々目も向けない閉鎖的な雰囲気が強いことも感じている。僕は「尊敬する」日本から来た人間として、彼らの前に立って話をするに相応しい人間だろうか。旅の後半に控えている講演を思い、色々と考えずにはいられなかった。
心ゆくまで歓待を受け、ほんのちょっぴりウォッカに顔を赤らめながら夜は更けてきた。実はこのツアーの特色として、首都での滞在先がキルギス人宅へのホームステイだということが挙げられる。普通に観光しているだけではわからない人々の内面を、一緒に寝食を共にすることで感じていこうというものだ。キルギスの大学には日本語学科もあり、多くはないとはいえ日本語話者もいる。そういった日本に興味を持つ多くの人々が、日本人観光客のホームステイ先として手を上げてくれたのだ。僕のホームステイ先の人は、日本語を勉強しているわけではないが、東アジアの文化に強く興味を持つ家族だった。財務省で農作物のマーケットに携わる仕事をしているベルメットさんと、その息子で秋からマレーシアの大学留学を控えているバッハのふたり、素敵な笑顔を持った母と子との出逢いだった。
会話は英語で行われたが、すぐに意気投合し、様々な話題に話は及んだ。僕はキルギスの社会問題や、その特殊なイスラム社会(キルギスには宗教というより文化としてのイスラムが根付いている。日本が仏教を文化的背景としているのに近い)に興味があった。ベルメットさんやバッハは東洋の思想、文化に興味を持っていて、漫画の話から禅の思想まで、幅広く語り合った。僕はキルギス滞在1日目にして、キルギスにも家族ができてしまったのだ。

3.イシク・クルの朝日
翌日、僕達はビシュケクを後に、東に位置するキルギス最大の湖、イシク・クルを目指すこととなった。快晴の青空がどこまでも続く中、僕達は一路東へ走った。その途中で10世紀から残る遺跡、ブラナの塔を訪ねた。ここはシルクロード上に位置しており、昔はその周辺の市場が大変栄えたという。塔の上からは果てしない草原が視界に広がる。ここを多くの人々が往来したのかと思うと胸が高まった。いつかシルクロードを端から端まで歩いてみたい。そんな思いが沸き上がってきた。人が古代の歴史へと想いを馳せるのはなぜだろう。きっとそこには遺伝子に組み込まれた太古への郷愁、脈々と受け継がれて来た人間の営みに対する畏敬の念があるのではないだろうか。傍らを吹く風に、数百年、数千年の人類の流れを感じた。
昼食はキルギスの一般家庭をレストランに改装した場所で、伝統的な料理を満足行くまで食べた。キルギスでは客人をもてなすことは当然の美徳と考えられており、食べ切れないほどの料理を振る舞う。家計に余裕のない家庭でも、借金をしてでも客を歓待することがあるという。これは長く受け継がれてきた遊牧文化の特性ではないだろうか。次いつ会えるともわからない遊牧中の出会いに対し、「旅は道連れ世は情け」という価値観を醸成してきたのかもしれない。

昼食後の眠気にうとうととしながらしばらく走ると、あたり一面山脈に囲まれている平野に出た。その峰々は遙か高く、ここでは3〜4千メートル級の山は普通の珍しくもないという。ちなみにキルギスの最高峰はポペーダ山の7,429メートルということだから、日本の誇る富士山も小さく思えてしまう。
日の沈む前にはイシク・クルへ着いた。キルギス最大の湖は、湖というには余りにも大きかった。琵琶湖の9倍もの面積を持ち、その最深部は668メートルだという。イシク・クルとは「熱い湖」をいう意味らしく、極寒の冬でも凍らないという不思議な性質からそう名付けられたという。湖底には多数の遺跡が水没しており、考古学者の探究心を刺激している。そんな湖の畔でのんびりと過ごしたあと、ゲストハウスのオーナーに招かれ夕食を取った。ここでもまた素晴らしい料理に迎えられ、各々のショットグラスには特上のウォッカが注がれた。キルギスにはもともとアルコール度数の高い酒はなく、ウォッカなどの強い酒はロシアから入ってきたという。みな客人の歓待のためにと杯を掲げ、数多くの乾杯が続いた。これはホームステイ先で聞いたことだが、キルギスでは乾杯を非常に大切にするという。日本で乾杯といえば、飲み始めの合図代わり程度のものであることが大半だが、キルギスでは飲んでいる最中にも何回も乾杯があり、その乾杯ごとに誰かが心を込めたスピーチをする。一緒に目の前にいる相手の幸福を念じ、心の底からの言葉で祈りを捧げた後に杯を合わせるのだ。何度も何度も杯は交わされ、夜は心地良い酩酊と共に深まっていく。最大の歓迎の印である、羊を丸ごと焼いた料理を平らげたあと、皆の笑い声の余韻に浸りながら外へ出た。湖の畔から空を見上げると無数の星が頭上に瞬いている。なんと美しい星空なのだろう。アフリカの奥地で見た星空が脳裏に蘇る。くっきりとした天の川が絹を中空に舞わせたように煌めいている。目の前で静かに揺れる果てしない湖面と無限の星空を前に、この世界の広さを感じた。こんなにも広大な世界の中で、ほんの僅かな命の時間を過ごし、こうして多くの人との出逢いを紡いでいく。なんて不思議で、素敵で、限りない喜びなのだろう。深夜まで笑い声が折り重なり、夜は更けていった。
翌朝、イシク・クルに昇る朝日を見たいと思い早起きをした。世界中どこに行っても朝日を見たいと思ってしまう。それは言葉に表しがたい程に美しく、神秘的だった。大きく息を吸い、また新たに始まるキルギスでの一日に胸を踊らせながらシャッターを切った。

4.シベリア抑留者の遺産
イシク・クルの北岸から南岸へ向けて車を走らせる。途中の街で、ロシアの中央アジア探検家、ニコライ・ミハイロヴィチ・プルジェヴァルスキーの記念館と墓を訪ねた。中央アジア、山脈の奥の世界に魅せられた探検家は、5度の探検で中央アジア各地に赴き、イシク・クルの袂で息を引き取った。その墓は今も、本人の希望によってイシク・クルを眺望出来る丘の上に佇んでいる。今も昔も、中央アジアはどこか神秘的で、甘美な魅力を放つ土地だったのかもしれない。見たこともないものを見たい、出会ったことの無い人々と出会ってみたい、そのような欲求は人類に普遍的なものなのだろうか。
次に訪れたのはドゥンガン・モスクという100年前に建造されたモスクだった。中国の建築様式で立てられたイスラムのモスクは非常に珍しく、この建物は一本の釘も使わずに木材だけで建てられている。この建築技法は中国の秘伝であったため、建造した建築家は中国へ帰国した後処刑されてしまったという。様々な文明、文化、宗教の入り交じるシルクロード上のキルギスならではの珍しい歴史的建造物だと言えるだろう。
この夜はユルタと呼ばれる伝統的な遊牧民の移動式テントに宿泊することになった。既に陽も落ち暗闇に包まれる中、悪路をひた走り山の中腹を目指す。車のヘッドライトに照らされた道には、時折轟音を立てる濁流が目に入った。崩れそうな橋を何度も渡り、四方を山に囲まれた平野へと出た。モンゴルのゲルを彷彿とさせる移動式テントだが、その最大の違いは中央部の柱がないこと。うまく格子状の木材で構成されたテントは、約2時間でその組み立てが可能なのだという。羊毛で覆われた室内は、夏涼しく冬温かい快適な空間だ。満点の星空のもとキャンプファイヤーを囲み、皆で歌を歌って過ごした。


広大な湖を傍らに見ながら旅を続けているが、このイシク・クルの畔には、もうひとつ、日本人にとって大変興味深い建物がある。それが現在キルギス国防省の管轄となっているサナトリウム(療養所)である。このサナトリウムには泥湯などを利用する治療施設があり、現在も多くのアスリートらが利用している。なんとこのサナトリウムは、1946年から1948年にかけて、ソ連の捕虜となりキルギスに抑留されていた日本人らが建設したものだという。当時収容されていた日本人抑留者は125名。気候風土の良いこの地では、他の抑留地と違いひとりの死者も出さずにみな帰国したという。(一説にはキルギスの他の地方にも抑留されていた日本人がおり、その方々の墓があるという話もあるが未確認)。
実際に来ることになるまではその場所すらも曖昧にしかわからなかったキルギス。そこに日本人と由縁(ゆかり)のある歴史が存在するなんて思いもしなかった。僕の父方の祖父はシベリアに抑留されていた。祖父と同じように、ここキルギスにも沢山の日本人が連れてこられていたのだ。世界が如何に繋がっているか、またも自分の狭い世界の価値観を砕かれたかのような思いだった。この建物が今も変わらず治療施設として利用されているというのは嬉しい事実だった。屋内の一室には日本人抑留者が再訪して作った資料室もあり、管理人は若い日本人旅行客の来訪を心より喜んでいた。キルギスに抑留されていた方々の中には存命の方もいるということだから、いつかぜひその話を聞きたいと思う。様々な縁(えにし)に導かれながら歩く旅も、そろそろ終わりが近づいていた。

5.再会を約束して
再び首都に戻り、ホームステイ先の家族と再会した。ほんの数日離れただけなのに、随分と懐かしい気がする。翌日、国立のアラ・アルチャ自然公園へと足を運んだ。ホームステイ先の息子、バッハもこの日は一緒に来てくれた。50以上もの山の峰に囲まれた自然は壮大で、深呼吸をすると体の隅々まで洗われるようだった。ここではのんびりと大自然の中で食事をしたりゲームをしたり、乗馬を楽しんだり、のんびりと過ごすことが出来た。沢山のキルギスの見どころを駆け足で巡る旅だが、なんといってもこの旅を案内してくれるキルギス人の仲間たちの協力がなければ全ては不可能だったに違いない。数ヶ月も前から念入りに準備を進めていたイバラットさん、ツアーガイドや運転手たち、日本人と交流したいと言って着いてきてくれた学生たち。みなの真摯な思いがあって初めて、僕達はこの国で心ゆくまでくつろぎ、楽しむことが出来るのだ。数日とはいえ、朝から晩まで共に過ごす内に、国境を越えた絆が出来つつあった。単に仕事として関わっているだけではなく、心の底からキルギスを楽しんで欲しいという思いが伝わってくる。


午後にはJICA(国際協力機構)の事務所を訪ね、局長にインタビューをお願いした。多くのキルギス人が日本の震災に心を痛め、励ましの手紙や援助の申し出を送ってきてくれたという話を詳しく聞きたかったからだ。事務所には数多くの手紙が寄せられ、震災孤児を養子として引き取りたいという申し出も数多くあった。JICAの支援を受けている法律アカデミーの会員らは、全員がその一日ぶんの給料を日本の震災のために寄付したという。首都ビシュケクの市長も日本への留学経験があり、本当に数多くのキルギス人が日本のために動いてくれていたことを知った。
午後にはキルギスでも有名な舞踊団のステージを見せて頂いた。東洋とも西洋とも思える出で立ちと、その力強い動きの舞踊に目が釘付けになった。こんなにも多様な文化、深い伝統のある国を今まで知らなかったなんて。世界には圧倒的に知らないことの方が多く、自分の持っている価値観なんて本当にケシ粒のようなものに過ぎないのだ。
夕刻、遂に僕の講演の時間となった。この瞬間のためにキルギスまでやってきたのだ。全ての思いをぶつける覚悟で話をしなければ。僕が話したのは東日本大震災の現状と、そこで失われたひとつひとつの命についてだった。大局的な数字で語られてしまうひとつひとつの死には、それぞれの痛みと、愛する人を失ったその何倍もの人々の悲しみが含まれているということを伝えたかった。イバラットさんのロシア語通訳を介して、来て下さった方々に、そして日本から一緒にやってきた仲間たちの心に向かって話す。楽なことではなかった。何度も口にしてきたし、出来る限り文章にも起こしてみた。それでも、震災で失った最愛の人との死別を語るには、いつも心の傷を抉る必要があった。僕がわざわざこの話をあちこちに出向いてまでするのには理由があった。人は他者の痛みを感じることの出来る生き物だ。そしてその悲しみや痛みはネガティブな感情ではなく、愛の裏返しであると信じているからだった。こんなにも多くの人が、キルギスの人たちが心を痛めてくれた。それは同じ空の下に生きる人間として、理屈を越えて感じる痛みのはずだ。絞りきれるだけの力を絞り言葉を紡ぎ、講演を終えると全身の力が抜けた。目の前の人たちに直接感謝の言葉を届けられたという安堵と、世界の絶望的な痛みを前に、自分の言葉はまだまだ力不足で、光を提示するには及ばないという挫折感を全身に感じた。
僕の講演の後、日本人の仲間たちが次々に旅の感想、そしてキルギスの方々への感謝を伝えていく。及ばない僕の言葉を後押ししてくれるように、それぞれがそれぞれの言葉で世界を紡いでいく。その姿を目にし、言葉を耳にし、改めて今回この旅に参加出来てよかったと感じた。国境や言語といった、様々な境界線が溶けていく。そう、世界はもっとシンプルでいい。ただ、目の前にあなたがいて、僕がいる。その総和が世界であり、みな大切な人を大切に思いながら生きて行きたいだけなのだ。キルギスで出逢った大切な人々がいるということ、それはまた僕の偏狭な世界の裾野を広げてくれた。
夜になり、ホームステイ先の家族と最後の時間を過ごした。キルギス滞在中に感じたこと、人々と出会えた幸せ、人生観についてなど、様々なことを話し、笑った。僕が想像していた以上に、彼らは僕を家族として受け入れてくれた。親族意識の強いキルギスでは、7代先まで遡って親族がいるという。袖振り合うも多生の縁、この出逢いにも大きな意味を感じずにはいられない。必ずこの家族に会いに戻ってくる、そう胸に誓い家を後にした。
後ろ髪を引かれる思いでビシュケクを後にする。その道の途中で車が故障したということで急遽道路脇に駐車した。こんな時に故障だなんて、飛行機に間に合わないかもしれない。タクシーを呼ぶしかないと思った時、背後でいきなり爆発音がした。何事かと思い振り返ると、それは花火だった。キルギスの旅をずっと世話してくれていた現地の仲間たちが、僕らの帰国のためにサプライズを用意してくれていたのだ。僅か数日を共に過ごしただけとはいえ、既に彼らは僕らの大切な人になっていた。その心遣いに日本人旅行者全員が感激していた。キルギス最大の湖、イシク・クルはその美しさ故「天山の真珠」と呼ばれている。しかし、真に美しいのは彼らの胸の内に光る温かな心なのではないか。天山山脈の麓に生きる彼らの、真珠のように光り輝く心に触れたことこそ、今回の旅での最大の宝物となった。
中国、ロシアに挟まれるキルギスは地政学的にアジアの要所であり、その空港はアフガニスタンに侵攻する米軍の重要拠点である。また、東部で採掘されるレアメタルは世界市場の微妙なバランスに影響を与えている。国家独立から20年、新政権の誕生から1年という若い国では、貧困や失業者、民族問題など、様々な問題に揺れている。世界各地の社会問題に関心を持つ僕は、ともすればそういう面に目が向きがちだった。しかし、今回のキルギスの旅で得たものは、とてもシンプルなものだった。そこには大切な人がいて、同じように呼吸をし、毎日を生きている。それを実感として感じられたことは、今後の未来を照らす大きな光となることだろう。この旅で出逢った全ての人に最大限の感謝を捧げたい。

寄稿者プロフィール

■ 佐藤 慧
フィールドエディター/ジャーナリスト studioAFTERMODE所属
大阪芸術大学音楽学科中退。世界を放浪。2007年に初アフリカ訪問。ケニアとタンザニアを旅する。その後、アメリカのNGO職員としてザンビアではHIV/AIDSや公衆衛生、中南米ではボランティア教師として働く。2009年、ザンビアでは学校建築プロジェクトを立ち上げ完遂。現在は、フィールドエディター/ジャーナリスト(studioAFTERMODE所属)として、ザンビア、コンゴ民主共和国を中心に取材。
東日本大震災で、両親の住んでいた町、岩手県陸前高田市の復興支援を行っている。震災で、最愛の母を失った。http://ryugaku.myedu.jp/edit/am/am4.html
★佐藤さんの寄稿「世界に魅せられて」は、「毎日留学ナビ」連載コラム参照。
http://ryugaku.myedu.jp/edit/am/
★佐藤さんのブログ:http://ameblo.jp/keisatojapan/
サラーム・キルギス・ツアーのお問い合わせ
【お電話でのお問い合わせ】
株式会社 毎日エデュケーション 担当:石渡・高橋
フリーダイヤル:0120-655153
【インターネットからのお問い合わせ】